三島・沼津の古道を探る
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
||
 |
 |
|
| 幸原堰から神池ルート・三島宮川用水(みしまみやがわようすい) 総延長約2km 川幅約1m内外 なお、幸原堰(こうばらせぎ)については現在追跡調査中です。 |
||
 |
||
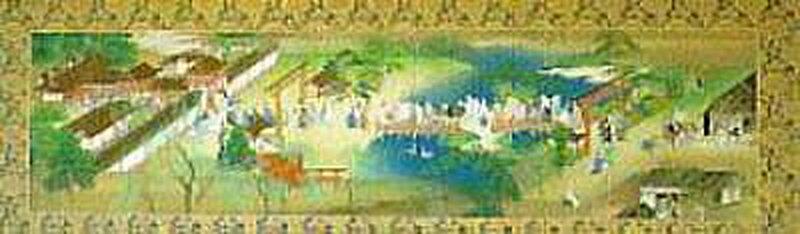 |
||
 |
|
|
| 神池の歴史を語る江戸時代の絵図 造営図をクリックしますと拡大します | ||
| 1604年・徳川家康三嶋大社造営図 | 1634年・徳川家光三嶋大社造営図 | |
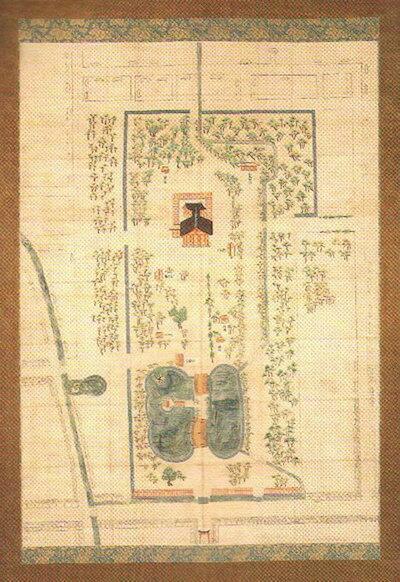 |
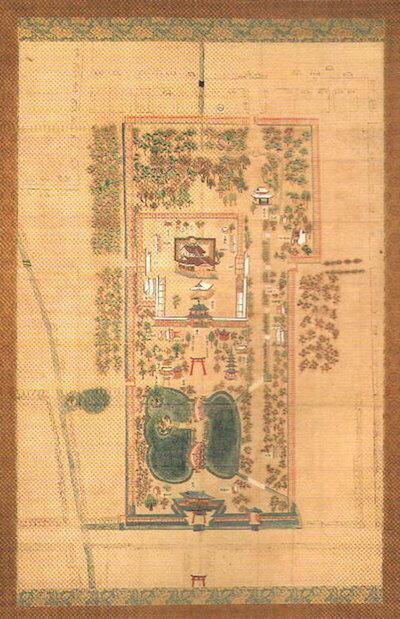 |
|
| 1654年・徳川家綱三嶋大社造営図 | ⇒1654年境内絵図の解説 | |
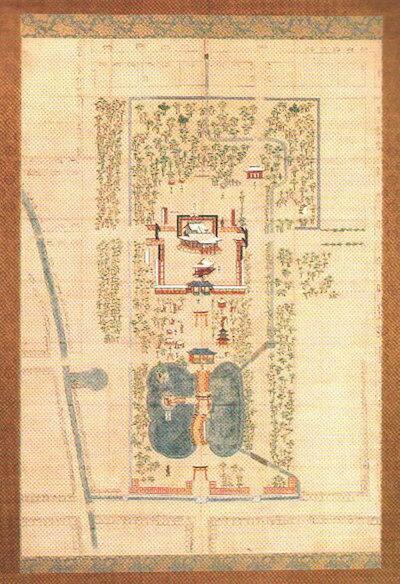 |
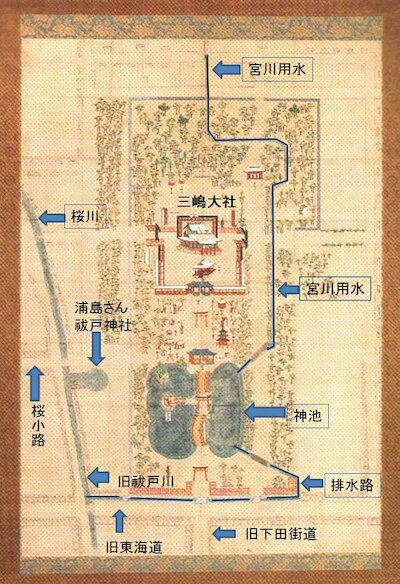 |
|
|
||
| 幕末(承応期頃)の三嶋大社絵図 絵図をクリックすると拡大します | ||
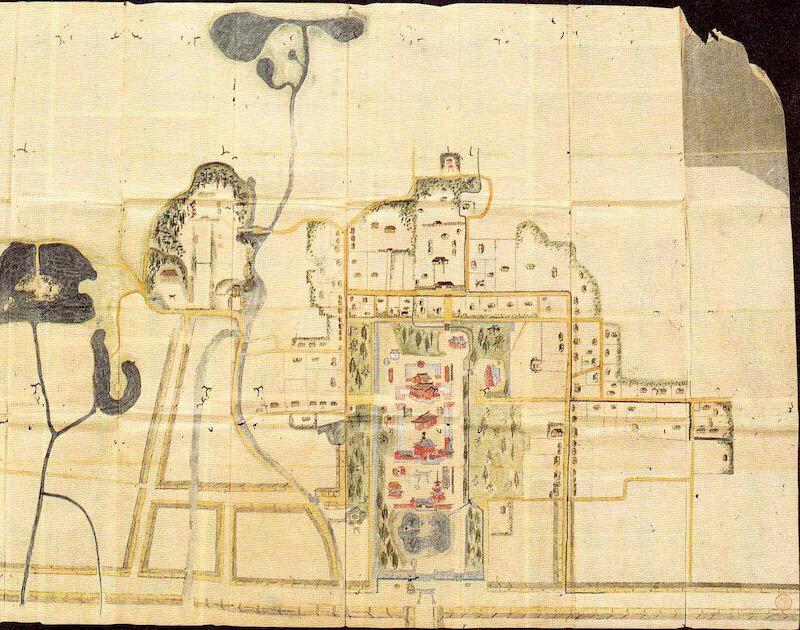 |
||
|
||
| 三嶋大社(みしまたいしゃ)の神池の歴史 | ||
 |
|
|
 |
||
| 幸原堰(こうばらせぎ)航空写真 Google Earthより画像作成 | |
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
三島・沼津の古道を探る

